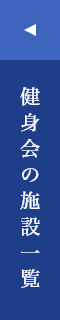ドナーとレシピエントの佐多ご夫妻が同一の病棟に揃った4月5日には移植のマネージメントはすでに最終段階に入っておりました。ご夫婦の精神科的評価をいただけば倫理委員会に提出する書類は完成ですし、実施検討委員会はほぼ同じものを使い回して、もっと文章を簡略化したのがPOCとなります。そろそろ手術当日の人員配置やアルバイトの調整に入るところでありました。
4月7日土曜日は寒い日でありました。病棟に届いていた病理結果を見て目が飛び出たのを今でも憶えております。ドナー候補の睦子さんの胃潰瘍からたった1つ採取した生検結果は “group V, adenocarcinoma” であり、なんとドナー候補は胃癌でありました。真っ先に思ったのは「あのご夫婦になんて話そう?」と言うこと、「生検なんかするんじゃなかった!」との思いも頭をよぎりました。確か教授と袴田、鳴海、豊木先生らは医局にいたはず、と研究棟まで走って戻りました。
病理結果をお話ししたところで一同に溜息が漏れました。蚊の鳴くような「なんとか、胃切除とドナー手術を同時にできませんかねぇ〜?」と、私の言葉は虚しく語尾も弱く、その場は静寂に包まれました。鳴海先生は窓から曇り空を眺めて口を閉ざしています。佐々木教授はチッと舌打ちをして腕組みをしながら首を傾げ、袴田先生もうつむいて無言を貫き、豊木先生に至っては不意に部屋から出て行ってしまいました。この光景は、メジャー初ホームランを打った大谷翔平選手をナイン全員が無言で迎えたエンゼルスベンチの「サイレント・トリートメント」のようでありました、状況は激しく違いますが。最初に口を開いたのは佐々木教授でした。「うん、まあ、なんだ、とつかくん!、今回はドナーが小さくて、やらなくて正解だったかも分からんよ!」と言われました。「ああっ!、論点がずれた!」と私は直感しましたが、前の年の1月に経験した成人間生体肝移植で移植肝が極めて小さく機能不全に苦しんだ経験から絞り出た言葉、言うなれば教授の本音だとすぐに理解しました。